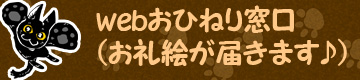クロックロの事件簿
|
著作、宮部みゆき
ノアエディション(フリーペーパー社)に雇われている前畑滋子の元に、中年女性・敏子が訪ねてくる。敏子には夫はおらず、40歳を過ぎてから産んだ一人息子・等を事故で失ったばかりだった。敏子は等には超能力があったのではないかと思っており、滋子に捜査を依頼に来たのだ。 等が生前に描き残した絵には不思議なものがあり、それがサイコメトラー能力のなせるものではないかというのだ。 滋子はこれを敏子が息子の死を受け入れ、思い出にするための「喪の作業」ととらえ、依頼を受けることにする。 その過程で、焼け跡から16年前に失踪した娘の遺体が発見された土井崎家が絡んでくる。娘を殺したのは両親だったが、すでに時効は成立しているのだが――。 ※ネタバレあり 象のような 敏子を指した表現です。友達に「お前の母ちゃん、象みたい」と馬鹿にされたときに、等が胸を張って「象は目が穏やかなんだ。知性があるからだよ」と答えるエピソードが好きです。初見時、「そうか、象の目は穏やかで優しいんだ……知性があるんだ……」と、象への見方が変わった覚えがあります。以来、象の顔を意識して見るようになりました。 「ドンペリの墓標」 とても象徴的な表現だと思います。 千里眼の教主と、その信者たち。 敏子の家を表したものです。わかりやすくて面白かったです。 「この絵をずっととっておきなさい。これが、あなた方の若い魂が今現在認識している世界の姿です。そして、いつかこの絵を一抹の含羞と深い愛情を持って眺めていられるような大人になりなさい」 ティーンエイジャーに描かせた絵は、親から必死に分離しようとしている時期なので、とても尖っている。そういう時期に描かせた両親の肖像画はものすごいのだと言います。
滋子と初めてあった野本刑事の態度について。 人生が外側から破壊される瞬間。 野本刑事の台詞はどれも愚直で、まっすぐに誠子への想いが伝わってきてグッときます。
滋子が松夫を説得しているときの言葉。 「何をやったって、等が戻ってくるわけじゃないでしょうが」 思い出は大切です。 大人の態度だ。肯定しないが否定もしない。その間隙に、超能力は「存在」し続ける。 「大人の態度」「肯定しないが否定もしない」「その間隙に」「超能力は『存在』し続ける」 額がかなりあがっていたが、それが押し出しを良くしていた。 高橋弁護士に関する描写です。 気丈さが過ぎて、強がりが混じってきた。 誠子が別れた夫について語った時の描写です。 頭と尾がつながってぐるぐる回り、太っていく。 噂についての描写です。 「悪いことの場合は、言ったら言った方の勝ちで、言われた方は信じないって思っていても、やっぱりどこかで気になるものです。そういうやり方で他人様の心に踏み込むのは、他所のうちに土足であがり込むのと同じですよねえ」 本当に敏子は聡明で立派です。それを感じさせない態度がまた素晴らしいと思います。もちろんそれはフィクションのキャラクターだからなのですが、現実でも、こういう人を目指したいなと思わせてくれます。自分がもう少し年を取った時に、どんな印象を他人に与えられるかを常に考えて生きていきたいです。 罪の意識を持つ者は、追われずとも逃げる。 真理です。 「まだお父さんとお母さんを怒ってるんじゃないの」 誠子が、なぜ茜が帰ってこないのか母に尋ねたときの返答。 ああ、本当にいい人だ。滋子の知りたいことを全部教えてくれた。 あおぞら会の荒井事務局長に対する描写。皮肉っぽくて面白いです。
滋子が、「死の山荘」事件に関わって知ったことです。
茜について、誠子の幼馴染の母が言った言葉です。 茜ちゃんは、大人の茜さんになることはなかった。 読んでいるこちらが悲しくなってきます。茜は悪い評判しか出てこない子ですが、それでもやっぱり悲しいです。 誰もが義務や権利という概念では感情を整理できない時にこそ義務や権利から目を離さずにいるのが弁護士の仕事 立派な仕事だと心から思います。 テーブルの下に入り込もうとしてでもいるかのように 土井崎夫妻に対する描写です。 最早、過去の秘密から誠子を遠ざけておく手段はない。シゲはいつでも、好きなときに口を開くだろう。考え得る二種類の厄災のうち、最悪なものから誠子を守るためには、自ら罪を明らかにするしかない。 「厄災」という表現が秀逸です。まさに夫妻にとってシゲは「天罰」であり、落とされる罰は「厄災」なのでしょうね。 説得しきれたとは思えないが、動かすことはできたのだ。 胸に来ました。 「土井崎さん」 「届いた」というところは、物理的な意味だけではないのだろうなと思います。
ギャンブルのようなその場の快楽。すべてが終わったら現実に戻る。そして支払った代償の大きさに震えるのです。
気になる点。 結局、一番最初のトラックの絵は何だったのでしょうか。
(クロックロの書斎LINEスタンプ) ▲ホームへ戻る ▲クロックロの感想文へ戻る ▲一番上へ戻る |
◆目次◆
PR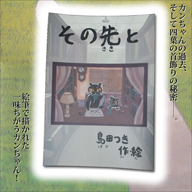
絵本「その先と」書籍版(B5判)
『楽園』
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
関連商品
『模倣犯』
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |