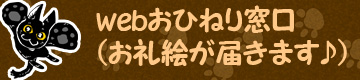クロックロの事件簿
|
著作、宮部みゆき
ノアエディション(フリーペーパー社)に雇われている前畑滋子の元に、中年女性・敏子が訪ねてくる。敏子には夫はおらず、40歳を過ぎてから産んだ一人息子・等を事故で失ったばかりだった。敏子は等には超能力があったのではないかと思っており、滋子に捜査を依頼に来たのだ。 等が生前に描き残した絵には不思議なものがあり、それがサイコメトラー能力のなせるものではないかというのだ。 滋子はこれを敏子が息子の死を受け入れ、思い出にするための「喪の作業」ととらえ、依頼を受けることにする。 その過程で、焼け跡から16年前に失踪した娘の遺体が発見された土井崎家が絡んでくる。娘を殺したのは両親だったが、すでに時効は成立しているのだが――。 ※ネタバレあり 9年前の事件――滋子はあの事件以後、精神的に折れてしまい、ルポライターとしての活躍はできず、「死の山荘」に関する著作も残していませんでした。にもかかわらず、敏子が依頼相手として前畑滋子をわざわざ選んだのは、「死の山荘」事件に関わったライターだったからだといいます。事件当時のルポを読み、関心を持ったということです。 世間はまだ、当時のことを忘れ切ってはいないのです。滋子のしてしまったことも。 『楽園』内では遠まわしな表現で、滋子が何にそこまで心をさいなまれているのかわかりませんでしたが、『模倣犯』を読んだ後だと、この点の重みがよく伝わってきます。 この作品では、模倣犯の頃から9年が経ったことで、滋子の心にも成長や変化が見られるところが印象的です。
夫・昭二の両親への気持ちの変化は特に感動しました。
一方、当時、サブリナでお世話になった編集長とは今も疎遠のままです。
逮捕されてからもあんなに余裕綽々だったピースも、現在では精神をやられて拘禁反応が出ているそうです。
山荘事件で滋子がどんな関わり方をしたのか、はっきりと触れられた書き方は『楽園』の中ではされません。「ああいう形で関わった」などの遠まわしな表現がとられます。
敏子の家は、敏子の祖母・刀自の「ちや」に支配されていました。「ちや」は拝み屋をしており、超能力があったというのです。 滋子は敏子へのひどい扱いに怒りを覚えます。
やがて敏子には兄の計らいで恋人ができるのですが、いろいろな事件やしがらみがあり、その恋は叶いませんでした。 そんな家族に滋子は思います。 困って困って、そろそろ自分たちの頭で考えることを始めるいい機会だったのだ。 ここには共感しました。 敏子とほかの家族の交流は、ちやの葬儀で最後となります(松夫兄以外)。 ちやの骨を拾ってはいない。 というのが、これ以上ないほどに、最後まで埋まらなかったちやとの溝を読者に感じさせてくれます。
彼女からもまた、「死の山荘」についての話が出ます。彼女はドキュメンタリーを見たのだと。そして、ただひたすらに怖かったのだと。
これを描けてはいけない。普通の人間に描けていいものではない。 描くことができないほど恐ろしい。そういう意味では、「僕は模倣犯なんかじゃない」というピースの主張は正しかったことになります。皮肉ですね。
花田先生は、この男に芸術の素養があることが恐ろしいと言います。
また、「子供は親の絵はうまく描けない」という話は興味深かったです。まだ自分と分離できていないからだと。
滋子は夫・昭二との間に子供は恵まれませんでした。
滋子は、等くんの絵がなぜ、一部のみ幼稚園児が描いたように退行するのかを花田先生に質問します。 「子供が、怖い思いをしたときです。自分の手には負えない、理解できないものに直面したときです。小さく、幼くなって、そこから逃げようとするときです」 人間は怖い目に遭うと幼児退行する。その事実そのものが怖いな、と思ってしまいました。
そういうことじゃいけないの?
という、直美の言葉が胸に来ます。
「それ、誰かが知ってたなんて、むごいじゃない」
と。 そして、別れ際、直美は滋子にいいます。 「あたしたちが心配してるって、伝えてくれる? セイちゃんとは今も友達だって。身体に気をつけるんだよって」
友達に何かがあった時にこう言える人間でありたいものです。
(クロックロの書斎LINEスタンプ) ▲ホームへ戻る ▲クロックロの感想文へ戻る ▲一番上へ戻る |
◆目次◆
PR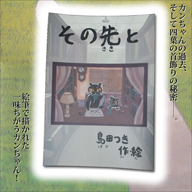
絵本「その先と」書籍版(B5判)
『楽園』
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
関連商品
『模倣犯』
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |