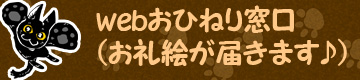クロックロの事件簿
|
著作、宮部みゆき
※ネタバレあり 『模倣犯』を読んで以来、宮部みゆき作品を順番に読んでおります。 『おそろし』は江戸時代の怪談物語。一つ一つの話が短くて読み易いです。 読んだ感想は……「あ、これ松太郎に萌えるやつだ」(ヒロミくんはどうしたんだよ!!)。 主人公・おちかは丸千という宿の娘でした。 また、江戸の文化や生活があふれていて読んでいて楽しいです。
〜一話目、「曼珠沙華」〜 そして、人を恐れさせる恐怖の対象が自分だったという恐怖。 〜二話目、「凶宅」〜 清六は頑張ったんですね。自分の命と引き換えに、家を燃やすまで。 ラスト、座敷牢を忌んでいた家の娘が座敷牢に入れられることになるところがやるせないです。 おたかさんがおちかに遭ったことを知っているところが怖いです。 〜三話目、「邪恋」〜 はじめ、松太郎を最初に見つけた行商人と、丸千で、どちらが彼を引き取るかでもめます。 良助は年頃になると素行不良が目立つようになり、それを落ち着けるためにおちかとの結婚話が持ち上がります。 読んでいてとても苦しくなります。 おちかはといえば、松太郎のことを好きではあったのです。松太郎がそうだったように――。 おちかのなかには十四の小娘の本気があった。 「でも線引きはしていた」。 松太郎が好きという想いに固執できるほどには、まだ女になりきってもいなかった。 そして三年後、まともになった良助から、改めておちかに結婚の申し入れがあります。 結婚前、裏庭で逢引しているところに松太郎が現れます。 ――おめでとうございます。良助さん、どうぞお嬢さんをよろしくお願いいたします。 これが良助の逆鱗に触れます。「お前なんかがおちかをよろしくだと。身の程をわきまえろ、野良犬め」と。 これに対して松太郎の答える、 ――ただ、俺は本当にお嬢さんに幸せになってほしくって。 の切なさ。胸を締め付けられます。 けれど、良助も辛かったのだということが読んでいてわかります。 「二人を一度に取り戻し」という表現にもその心情がよく表れています。 これは丸千が最低だということでしょう(しかしこの感情も、最後まで読むとひっくり返るからこの小説はすごいのです)。 これでもかというくらいに良助に罵られた松太郎は、良助に肩を抱かれながら離れようとするおちかに投げかけます。 ――おちかさんも、俺のことそんなふうに思っていたんですか。 辛い。辛すぎる。 激高した良助が松太郎に殴りかかりますが、今度は松太郎も抵抗します。本気を出せば良助よりも手負いの松太郎の方が強かった。そういうところにも萌えますね。 先に鉈を手にしたのは良助です。鉈を取り上げて松太郎は良助を殺してしまいます。 おちかにこう言い、かつて拾われた崖から飛び降り自殺する松太郎。 正当防衛とまでは言えなくても、松太郎を強く責めることのできる話ではありません。 良助を選びながらも、松太郎を完全に切り捨てるわけでもなく。そういう自分の卑怯さが、松太郎を最も絶望させたのだろうとおちかは考えます。 良い子のままでいて、松太郎にも憎まれたくないか。 きっとおちかは、叔父叔母夫妻の家で奉公人として働くことで、松太郎と同じ境遇を望んでいるのでしょう。家族でも奉公人でもない、半端な立場に置かれた松太郎と同じ境遇を。 しかし、「松太郎と所帯を持たせる」と言っていたのは三年も前の話なわけで。それだけ年月が空けばおちかや周りの気持ちが変わることも普通にあるかと思うのです。だからそのことで、松太郎をぬか喜びさせたというのも何か背負い込み過ぎかなという気がします。
咳の療養のために離れて暮らしていた姉が、年頃になって戻ってきたら、兄と恋に落ちてしまったというお話。 そんな中で、ほとぼりが冷めて帰ってきた兄に、妹のお福は「姉の形見だ。姉さんを思い出すたびに覗いてごらん」と手鏡を渡されます。「母さんたちには内緒だよ」とも。 これがばれたとき、母親に兄がすらすらと嘘をつくところが怖いです。 結局、お福の暮らす石倉屋は滅んで終わりました。 しかし、お福は現在、幸せに暮らしています。そのことは同じようにつらい目に遭ったおちかにとっても、救いになる話です。 「ならば、わたしの家で起きた不幸は誰のせいになりますでしょうね? 姉ですか。私たちの姉のお彩が、すべての罪科を背負うべきでございましょうか。実の弟をたぶらかし、人の道を踏み外させただけでは足りなくて、死んだ後も妄念を残し、石倉屋の者たちに災いをもたらした。ええ、とんだ悪女でございます。お彩はそういう、悪いことをするためだけに生まれついた女っだったんでございましょうかしら」 そして、松太郎に対する丸千の人たちの行動についても。 「わざとしたわけじゃございませんよ。松太郎さんを不幸にしようと思ってなすったことじゃございません」 人間誰だって、そのつもりがない行動で、人を不幸にすることがある。でも、わざとそうしたわけではない。誰もが心の中にくすぶらせている疵を癒してくれる台詞です。 子供の頃のお福は死んだ姉が夢に出てきて怯えていました。そんなお福に、女中は「姉がどんな表情だったのか」を聴きます。姉は自分の顔を見て笑ったとお福が答えると――。 ――なんだ、それなら何にも怖いことなんかございませんよ、お嬢さん。 この女中の言葉がお福を救います。 亡者に命をあたえるのも、浄土を作るのも人の心だと。 このように、いろいろな人の業を背負った話を、「百物語」という形で受け止めることによって、おちかの心は少しずつ少しずつほぐれていきます。 お福を連れてきてくれた女中・おしまに、おちかが思った気持ちは複雑です。怒っているわけではない、けれど――。 踏み荒らされた気がしたのだ。 たぶん、どうされたって、どう接されたって、受け入れられない時期というものが人間にはあります。だからこそ、普通に生活を続けたり、他の人の話を聴いたりして心を整理する時間が必要なのです。
おちかの元に喜一兄さんが訪ねてきます。単に様子を見に来たというだけではなく、心配を抱えているようでした。 松太郎は恨んだり怒ったりしている様子ではなく、迷子で途方にくれているような態度だったそうです。 話を聞くうちに、おちかは嫌な思い出だけでなく、よかった部分も思い出すようになります。 「兄さん、懐かしいね」 おちかの心情には胸が詰まります。作中で一番心に残りました。
ここから急に話のテイストが変わってきます。 今まで登場した死人の魂が集合し、みんなで立ち向かっていくという少年漫画のような熱い展開になります。 これはこれでよかったのですが、展開もあっけなく、拍子抜けするラストでした。 それでも、みんなが助かって、松太郎とも話ができて、おちかは前を向けて、ハッピーエンドとなるところはよかったです。 「蔵」は引き込みたかったんじゃない、ずっと出たかったんだな……というところは胸がぎゅっとなりました。
結局、おちかの気持ちもどちらにあったのやらですし、蔵の番人の言う通り、良助が可哀想すぎます。 わざとそうしているであろうところが、宮部さんの妙技です。
(クロックロの書斎LINEスタンプ) ▲ホームへ戻る ▲クロックロの感想文へ戻る ▲一番上へ戻る |
◆目次◆
PR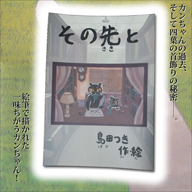
絵本「その先と」書籍版(B5判)
『おそろし』
 |
新品価格 |
![]()
関連
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |
 |
新品価格 |