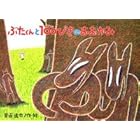|
女子高生が鶏を育てて解体して食べる 「命の授業」は残酷か?
〜クロックロ怒りのコラム
〜
2013年3月5日掲載
『情熱大陸』というドキュメンタリー番組で、福岡県のある高校を取り上げた。
その高校では、食品流通科一年で、毎年「命の授業」が行われる。鶏を卵のころから育てて、成長したら育てた生徒自身で解体して食べるという授業だ。この授業はメディアでも取り上げられ、文部科学大臣奨励賞も受賞している。
この番組について、松江哲明さんがコラムを書いた。
それを読み、自分はこの授業について知った。そして思ったことをこれから書きたい。
松江哲明さんのコラム
https://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130305-00000306-bjournal-bus_all
最初に言っておく。
今回の記事はこのニュースに対する所感というより、動物を使って「命の大切さ」を教えるという教育全般に対してとなっている。
そして小生は猫を名乗るほどの動物好きであるが故、一部感情的な表現が飛び出すかもしれないが、それもまた率直な気持ちとして寛大な心で受け止めてほしい。
解体の件は、食品流通科ということならギリギリ「あり」なのだろうか……ただ卵のときから名前をつけて、という辺りには疑問を感じる。
農家でもペットといずれ出荷する家畜は別に分けて、後者には情が移らないように分けて育てるという。
それを、名前を付けて愛情をこめて育てさせて、最後には解体させるというのは、教育というにはあまりに歪んでいるのではないか。
だいたい、普通、出荷するために育てる動物は、一匹だけを丹精込めてではなく、集団で育てるのではないのだろうか。それもできるだけ感情移入しないためではないかと思うが。
わざわざ感情移入する状態を作ったうえで、最終的にはどうあがいても死に向かわせるというのは、畜産業に歪んだ認識を持たせてしまう気がしないでもない。
そのあたりを教師はどのように考えているのだろう。
ただ小生は農家の人間ではないので、そのあたりはこちらのほうが認識に誤りがあるかもしれないので、深くは触れない。
このニュースを見て、真っ先に思い出したのが、「豚がいた教室」という映画だ。
これは、豚を飼育し、最後には出荷してその肉を食べるという取り組みをしている小学校を取り上げた映画だ。
豚には名前を付けて可愛がり、クラスメイト全員で世話をする。
小生はこの映画を見ていないし見るつもりもない。よって映画自体の批評はしない。
胸がつぶれる思いがしたのは、これが実話を基にした作品だということなのだ。
その事実だけで怒りが渦巻く。
「一年後に食べる」という約束で、豚をクラスで育てるという授業。
こんなのがあったら、自分なら間違いなく不登校になるね!
何が命を大切にするための授業だ。それを生業にしている人は、自分で選んでその仕事に就いている。それはとても尊ぶべきことだ。
けれど、子供たちにはなんの選択権もない。嫌かもしれないのに、授業だからムリヤリ飼わされ、食べるだ食べないだと話し合わされる。
教師の自己満足を押し付けられて、子供たちがあまりに可哀想だ。
お金をもらうわけでもない。生きるために食べるわけでもない。
命の大切さを教えるために人間を殺したりはしない。しかし、豚は殺す。こういうのを命を軽んじているというのだ。
子供の情操教育のためなら、豚の一生を弄んでいいのだね。
それこそ、命をないがしろにした行為だと思うが。
こういうものをさせることで食べ物を粗末にしないようになるのか?
この方法をとらずともいくらでも粗末にしなくなる教育はできるだろうし、そもそも食べ物を粗末にしないことよりも、命を大切にすることのほうがずっと大事だ。
一つの命を天秤にかけられる豚の気持ちにもなってみろよ。
こんなことをしたからといって、心やさしい人間にはならない!
猫ならダメ。犬ならダメ。豚ならいい。鶏ならいい。魚ならいい。
そういう問題ではない!
自分が愛情を込めて育てた動物なら、ザリガニや川魚だって殺せない。
それが命を尊く思うということだろう。
『星の王子さま』にも書かれていたが、時間を無駄にしたバラは、そのあたりにたくさん咲いているバラとは違う。仲良くなった狐は、その他の100万匹いる狐とは違う。
それが「仲良くなる」ということ。
食べるために育てるということと、飼いならすということは一緒ではない。
これを、「食べるべき」と言える人間は、想像力がないか、偽善者か、動物を飼ったことがないんだろう(違う、という人がいるならなぜ食べるべきと思うのか、教えてほしい)。
映画は否定しない。
だが、このような授業は許されてはならない。
どうして、「家族としての愛情を込めて育てる動物」と、「食べるために育てる動物」を同じ次元で語るのかと。それが本当に許せない。
もちろん、畜産用の動物も快適な生活をしたほうがよい。しかしそれは人間と家族としての絆を結ぶこととは別だと思う。
農家の人たちがお金をもらって背負う責任を、小学生に背負わせるべきではない。それはそういう仕事に就く人たちへの愚弄とさえ思える。
どうしても「命の教育」とやらがやりたいのなら、希望する生徒だけを農家やと殺場に連れて行って、見学でもさせてあげればよい。
学校教師が真似事でやるにはあまりにも責任の重たいことだと思う。
これが、実話だということに胸が潰れる。かつて、この世のどこかに、愛情たっぷりに育てられたあげく殺された豚と、愛情たっぷりに育てた豚を殺さなければならなかった子供たちがいるのだから。
直接命を奪わないと命の大切さが伝えられないなら、何百人もの人柱が必要だろう? ○○は犠牲になったのだ、教育の犠牲にな……。これではマッチポンプだし矛盾している。
それから、「子供にペットをあたえるのは教育にいい、死ぬ時には命の大切さを教えてくれる」という考え方には強く反対する。
動物を子どもの情操教育のために飼うという家もあるようだが。
命の価値は死ぬ瞬間には在らず 共に生きる過程に在り
そもそも動物は教育目的で飼うものではない。好きだから共に暮らすのだ。愛しているから共に生きるのだ。
動物を家庭に迎え入れるときは、人間が主体ではなく、動物を主体に考えなければならない。
人間で養子をもらうとして、実子の教育には兄弟がいたほうがいいから……などという理由で貰うのでは養子の子に失礼だろう?
それは動物でも一緒だ。
動物だからと軽んじる考え方をするのは、レイシストとなんら変わらない。
自分と違うものを慈しむ心を育てるには、下心があってはならないのだ。
特に「死ぬところをみせることで……」という考え方は、そんな気持ちで動物を幸せにできるのか自分は疑問だ。
まるで死ぬところを望んでいるかのような物言いではないか。
話を戻すが、教育のために命を犠牲にして、命の大切さを教えられるのか? 本末転倒ではないか?
ただ、今回のニュースについては、「食品流通科」とのこと。いずれはそういう仕事に就く可能性がある以上、家畜の飼育は訓練としてアリかもしれない。
だがそれを、決して、「命の尊厳を教える授業」などとは言わないでほしい。あくまで経験値を積むための訓練としてほしい。
また、名前を付けてペットのように可愛がり、最後には育ての親本人が解体するというのは疑問。
小生は鶏を飼っていた。鶏は人によくなつく。飼っていれば当然可愛い。愛情も湧く。
小生は鶏を食べるが、自分の家族として過ごした鶏を食べるのは無理だ。
それはまったく別の問題だと思う。
こういうニュースに感化されて、普通の学校でも取り入れようなどと考えなければいいと思う。
そこまで、現在の日本の教育現場が愚かとは思っていないし思いたくないが。
たとえば森で泣いている子猫を拾う。
「カンちゃん」という名前にする。
ミルクをあげたり下の世話をしたりする。
森を通りがかるたびにカンちゃんと出会った日を思い出す。
カンちゃんのお母さんや兄弟は元気にしているだろうか。
カンちゃんのことをもしかしたら探してやいないか。
そんなことを考えたら、育ての親として、カンちゃんを幸せにしなくてはと思う。
当然、死んだら悲しい、いなくなったら悲しい。
実際に体験しなくても想像するだけで胸が苦しい。
だから大切にする。
長生きを願う。
それが動物と暮らすということ、そして命を大切にするということではないか。
あえて「死」を見せることが、教育だとは思わない。
死から目をそらす子どもが、現実を知ろうとしない、感性が鈍いわけではない。
むしろ繊細だからこそ、見なくてもわかるのだ。わかるから辛くて見たくないのだ。
食べ物が牛や豚を解体したものだと直接見せなければわからない教育よりも、見せなくても想像させる教育が大切だと思う。
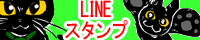
(管理人のオリキャラLINEスタンプ。よかったらこちらもよろしくお願いいたします)
▲ホームへ戻る
▲クロックロの事件簿へ戻る
▲一番上へ戻る
|